文化庁文化審議会著作権分科会が私的利用の違法ダウンロードの適用範囲を雑誌、論文など著作物全般に広げるとか。これは明らかに行き過ぎ。
著作物って「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)なので、コンテンツのすべてが著作物というわけじゃない。
松尾芭蕉の「古池や蛙飛び込む水の音」は著作物。
一方で、「今日の東京地方、午前は明け方から快晴でしたが午後からは雨が降っている。」これは事実表現なので、思想、感情を創造的に表現したものではないので著作物じゃない。
では、「古い池にカエルが飛び込んでポチャっという音がした。」が、本人が感情を表現しているなら著作物と言えなくはないが、客観的には事実表現。
このあたりが著作物とそうでないものの境界なんだろうけど、雑誌、論文にまで範囲を広げると著作物ではないものまで保護対象になっているという誤解が生まれて、その利用をためらってしまうので文化の発展を阻害してしまう。
これまでの保護対象は、明らかな著作物だったけど、雑誌、論文となるとそれが著作物なのかそうではないのか曖昧なところがあって利用者が判断のつかないグレーゾーンは利用を避けるようになるだろう。。
特に学術論文の科学の分野は実験事実の表現なので、考察以外の部分は、思想でも感情でもない。
ツイッターのつぶやきやブログ記事などに著作物といえるものは決して多くなく、運営上のエチケットや削除要請と削除の範囲に留まり、著作権侵害として損害賠償に発展するケースは限られているのではないだろうか。
何にしても著作権を過保護にすることはあまりいいことのようには思えない。

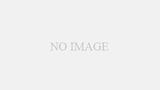
コメント