ご訪問ありがとうございます。
今日は、「茶」のツリーとティーとカラーのお話です。
「茶」には、植物としての茶樹と、飲むお茶と、茶色の意味があります。
茶樹は、葉も湯をさした飲み物としてのお茶もグリーンなのに、茶色はブラウンを表しますね。でも、紅茶、ほうじ茶、あとは、お茶ではないけど、麦茶、コーヒーなどもブラウンなので、飲み物としての「茶」というと茶色のイメージなのですね。お茶で染めた布も茶色になるのでそこに由来しているのかもしれません。
そこで枝豆の「茶豆」ですが、茶豆はどう見ても茶色ではありません。
莢に生えている繊毛が茶色だからとか、中の薄皮が茶色っぽいからだとか諸説があるようですけど、これは、素直に茶樹のグリーンから由来しているに違いないですね。
そもそも茶豆は、完熟すると茶色系の大豆になるなるわけで、茶色ならば、大豆こそが茶豆であって、枝豆のほうは、緑豆ですよね。そこをあえて茶豆というのは、やっぱり、茶樹のグリーンをイメージして「茶豆」と呼んでいるというのが私説です。
ちなみに「だだちゃ豆」は、だだ茶豆ではありません。
「だだちゃ」は山形県庄内地方の方言で「おやじさん」の意味で、ある「だだちゃ」が生産した枝豆がすごく美味しかったことからその品種が「だだちゃ豆」と呼ばれるようになったんですね。
これも私説ですが、「だだちゃ豆」と「茶豆」は、両方とも枝豆の品種なわけですが、歴史的には「だだちゃ豆」のほうが古く、山形県鶴岡市から新潟に「だだちゃ豆」が持ち込まれて「だだ・ちゃ豆」と解釈されたのではないか・・
つまり、「だだ漏れ」とか「だだ負け」「だだ黒」などの「すごく」とか「めちゃめちゃ」の意味の「だだ」に「茶豆」=「すごい茶豆」という名称だと思ったのではないか・・・
そして、自分たちが作った枝豆は、「ちゃ豆」と呼び、それが転じて「茶豆」になったのではないかと・・・・
本当のところをご存知の方がおられましたら是非教えてください。

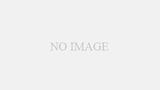
コメント